内科医に多いのが、不眠症にすぐ睡眠剤を処方してしまう問題です。半端な心療内科でも同じような傾向が見受けられます。
「眠れないのだから、睡眠剤でしょ!?」と思う人も多いでしょうが、睡眠剤には次のような問題点があり、実は違う薬の方がピッタリだったということもあり得ます。
睡眠薬の問題点
①睡眠剤による睡眠は、眠りの質が悪い
多くのケースで、睡眠剤で眠った場合、眠りの質は通常より悪化します。これは睡眠剤の効き方の特徴によるものです。
神経の興奮を静め、強制的に眠りやすくしたり、睡眠を持続させたりするような効果なので、深い眠りに導くような作用は無く、「浅いけれど、どうにか眠れている」状態にするのが、睡眠剤の効き方です。
睡眠剤を飲んで眠ると、朝起きた時に、全く体力が回復していないようなボーっとした状態になることが少なくありません。これは、ただ単に睡眠剤の作用が残っているからだ、と思うかもしれませんが、ほとんどの場合、そうではありません。というのも、多くの方が飲んでいる睡眠剤は、ハルシオンなどの「超短時間作用型」やレンドルミンなどの「短時間作用型」の薬なので、翌朝にそこまで薬の効果が強く残るというのは考えにくいからです。むしろ、これは睡眠剤による浅い眠りばかりで、脳が休まっていないのが原因です。
②耐性と離脱症の問題
睡眠剤を長期間続けて飲んでいると、睡眠剤がある状態に体が慣れてきます。睡眠剤の効果があれば眠れるため、脳は「眠れ」という指令を出すのをサボり始めます。サボりは徐々にエスカレートし、耐性(睡眠剤が効きにくくなる現象)へとつながります。同じ量の睡眠剤を飲んでいても、徐々に効き目を感じにくくなってきてしまうのです。
体の慣れ。これが睡眠剤の難しい点で、いざ「睡眠剤をやめよう」「睡眠剤を減らそう」とした時にも問題が生じます。
睡眠剤の量が減ったり、なくなったりしても、脳は「眠れ」という指令を急にテキパキと出せるようにはなりません。睡眠剤を飲み始める前より、眠るための信号が減った状態になっているのです。
何が起こるかというと、睡眠剤の量は減ったのに、脳の「眠れ」という信号は少ない。つまり眠れなくなってしまうのです。これを離脱症と呼びます。
睡眠剤で治療しているはずが、睡眠剤を飲む前よりも「眠る」ための信号が弱くなってしまうことがあるのです。
睡眠剤以外の選択肢
眠るための薬は、睡眠剤だけではありません。
睡眠を改善する代表的な薬に次の2種類があります。
- 体内時計を整える薬
- 抗うつ剤
体内時計を整える薬(例:ロゼレム)
人間の体の中では、メラトニンが増えたり減ったりして体内時計の役割を担っています。朝起きて日光を浴びると、メラトニンが徐々に増え始めます。夕方から夜にかけて、さらにメラトニンが増え、ある量以上になると眠気がくる、というような仕組みです。
このメラトニンと似た働きをする薬が、体内時計を整えるロゼレムという薬です。カンタンに言えば、「夜が来たよ、寝る時間だよ」と体に知らせてくれるような効果です。
ロゼレムのようなタイプの薬なら、睡眠剤であるように、離脱症や耐性もなく、やめたい時にはスパッとやめることが可能です。また、睡眠の質を改善する効果も期待でき、深い良質な睡眠をとることができる可能性があります。
ただし、効果はかなり穏やかな薬なので、ロゼレムを使うだけでは眠れない方もいらっしゃるでしょう。
抗うつ剤(例:リフレックス)
「抗うつ剤!?」と驚いた方もいらっしゃるかもしれませんが、不眠症には一番効果的になる可能性があるのが、リフレックスやレスリンのような抗うつ剤です。
抗うつ剤の中には、リフレックスやレスリンのように眠りやすくする作用を合わせもつ薬があります。こういった薬は、睡眠剤と異なり、浅い眠りを増やすというようなことはありません。むしろ、深い睡眠に導く効果も期待できます。さらに、メラトニンと同じく、耐性・離脱症がなく、やめたい時にやめることが可能です。
しかも、効果については申し分なく、眠りに入りやすくするだけでなく、睡眠を持続させる効果もあり、リフレックス・レスリンのような抗うつ剤、単剤で、睡眠に関する悩みが全て解消するケースもあります。ほとんどの不眠症の方に併発する、憂鬱な気分も同時解消できる可能性が高く、一番有効な治療法になり得ます。
将来まで見据えた選択を
目先のただ眠るということだけみれば、睡眠剤に勝る薬はありません。睡眠剤には、直接的に、かつ、協力に眠らせる作用があります。
しかし、眠れるようになり、
「徐々に薬を減らしたい」「やめたい」
といった時に問題が出てくるのが、睡眠剤です。耐性の問題も含まれます。
- 体内時計を整える薬
- 抗うつ剤
を効果的に使いつつ、それでも眠れない場合に睡眠剤を補助的に・短期的に使うという治療法ならば、そういった問題を軽減することが可能です。
目先だけでなく、将来を見据えて睡眠剤を使用するか否か、考えると良いでしょう。また、不眠の治療の場合、一般的な内科ではなく、専門の不眠外来や精神科、心療内科に通われることをお勧めします。

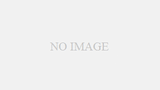
コメント